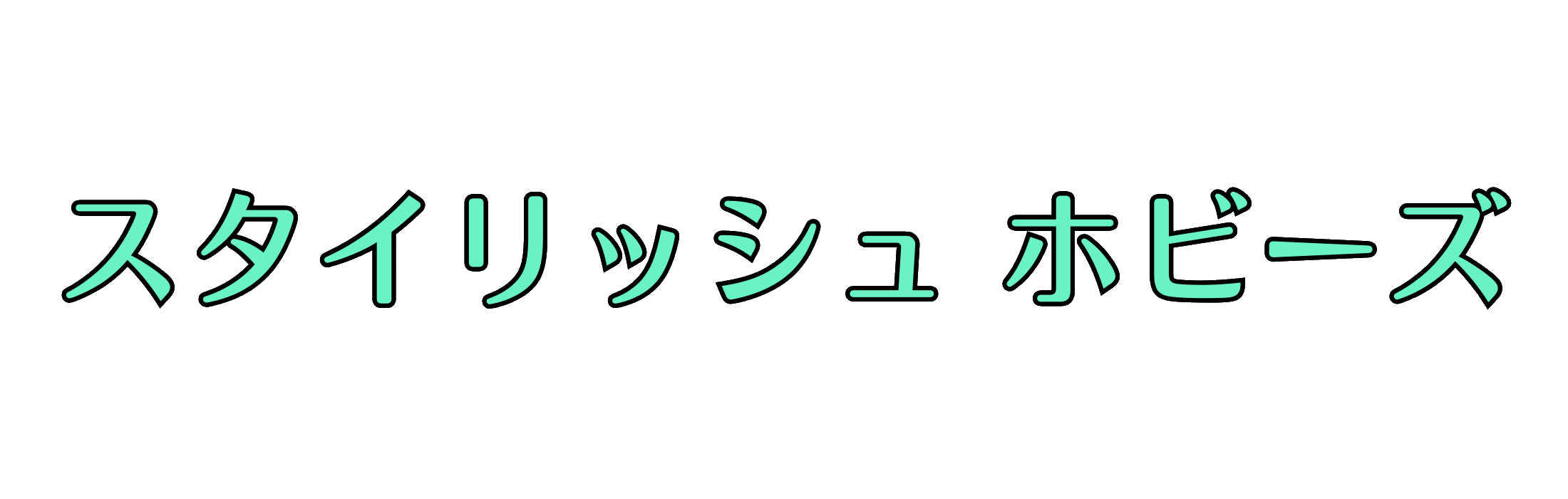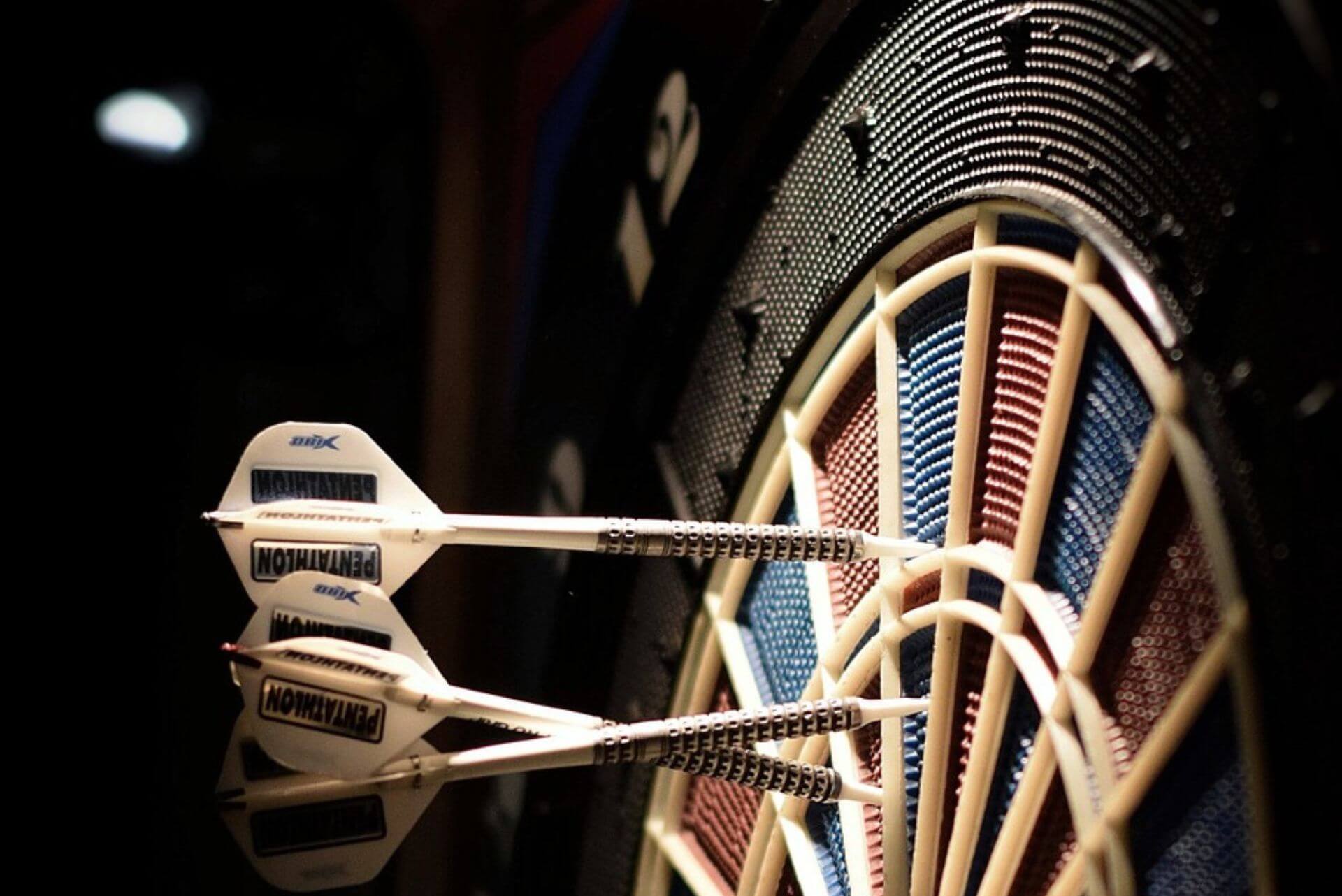「自宅で本格的にダーツを楽しみたい」
「お店のようなダーツマシンが家にあればいいのに」
と思ったことはありませんか?
とはいえ、業務用マシンは高額でサイズも大きく、個人で導入するにはハードルが高いのが現実です。
そこで本記事では、ダーツマシンの代わりに個人でも無理なく導入できる家庭用ダーツボードの選び方や、おすすめのセット商品、さらには設置方法のポイントまで丁寧に解説していきます。
これから自宅にダーツ環境を作りたいと考えている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
・家庭用ダーツボードなら、個人でも手軽に“マイダーツ空間”を実現できる!
・ソフトボードとハードボード、それぞれの特徴と違いをわかりやすく解説
・選び方のコツと、自宅用におすすめのモデルを厳選して紹介
・設置時の注意点や、快適に遊ぶための工夫も詳しく紹介!
業務用ダーツマシンは個人で購入できる?【結論】難易度高め

「ダーツマシン」と聞くと、バーやアミューズメント施設に設置されている業務用の大型マシンをイメージする方も多いかもしれません。
実際、DARTSLIVEやPHOENIXといった業務用ダーツマシンを購入することは個人ではなかなか難易度が高いです。
業務用ダーツマシンの現実:価格・サイズ・設置のハードル
まず業務用マシンの価格は数十万円から100万円以上と非常に高額で、現在はレンタルが基本です。
価格が抑えめの中古品も探せば存在しますが業務用ダーツマシン自体、サイズや重量も非常に大きく、広いスペースや専用の電源設備が必要になるケースもあります。
さらに、マシンによってはオンライン設定のため法人向けの専用回線の契約が必要になり個人が気軽に導入するにはあまり現実的ではないのが実情です。
個人利用に最適なのは「家庭用ダーツボード」
「ダーツマシン」と聞くと、多くの人は店舗やバーに設置されている業務用マシンを思い浮かべるかもしれません。
しかし、前述の通り業務用は本体だけで数十万円以上、設置スペースの問題や電源工事も必要な場合があり、個人で導入するにはハードルが高いです。
そこで注目したいのが、個人向けに作られた“家庭用ダーツボード”です。
機種によって「ダーツマシン」としての機能を持ちながらも、コンパクトで設置が簡単、そして価格も1万円前後〜3万円前後と手頃。
スマホアプリと連動してスコアを自動管理したり、オンライン対戦ができるモデルも登場しています。
家庭用ダーツボードには大きく分けて、
- ソフトダーツボード(素材:プラスチック)
- ハードダーツボード(素材:麻)
の2種類があり、それぞれに使用感や設置環境への適応度が異なるため、用途や好みに応じて選ぶことが重要です。
次のセクションでは、まずこの2タイプの特徴や違いについて詳しく解説していきます。
家庭用ダーツボードは2種類!ソフトボードとハードボードの違い

ダーツボードには大きく分けて 「ソフトボード」と「ハードボード」 の2種類があります。
見た目は似ていても、使用するダーツやプレイ感、設置方法、音の出方まで大きく異なるため、どちらを選ぶかは非常に重要です。
ここでは、それぞれの特徴とメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
ソフトボードの特徴とメリット・デメリット
ソフトボードは、プラスチック製のチップを使用するタイプのダーツボードで、主にゲームセンターやダーツバーで見かける「ダーツマシン」と同じ方式です。
■主な特徴
①自動でスコアを計算してくれるモデルが多い
②サイズ規格は15.5インチ(約39.4cm)が主流
③スマホと連動して全国のプレイヤーとのオンライン対戦や成績管理が可能なボードがある
④ボード表面に小さな穴が開いており、そこにダーツが刺さる構造
メリット | デメリット |
| スコア自動集計機能付きのモデルが豊富 アプリと連携して、対戦が可能な機種がある ボードの重量が軽めで、安全性も高い | ダーツが刺さる時の音がやや大きい ハードボードよりも弾かれやすい |
ハードボードの特徴とメリット・デメリット
ハードボードは、天然の麻を原料に製造された伝統的なダーツボードです。
プロの大会などでも使用されており、本格的なハードダーツ用です。
■主な特徴
①先端部分が金属製のダーツを使用
②サイズ規格はソフトボードよりもやや小さい13.2インチ(約33.5cm)が主流
③表面は柔軟な麻素材でできており、刺さった後に自然に回復
④自分で得点を計算する必要がある(電子機能なし)
メリット | デメリット |
| プロ仕様のリアルな打感を味わえる ソフトダーツボードよりも弾かれにくい ダーツが刺さる時の音が静か | スコアは手動で記録する必要がある ハードダーツは壁や床を傷つけやすい ボードの重量が重い(約4.5kg~5kg) |
どちらを選ぶべき?用途別のおすすめタイプ
家庭用ダーツボードを選ぶ際は、「どんな目的でダーツを楽しみたいのか」を明確にすることが大切です。
たとえば、家族や友人と気軽にプレイしたい、初心者や子どもでも安全に使いたいといったニーズがあるなら、ソフトボードが最適です。
ソフトボードは柔らかいチップを使うため安全性が高く、アプリと連携してオンライン対戦や自動スコア集計ができるなど、手軽さと機能性を兼ね備えているのが魅力です。
一方で、より本格的な投げ心地を求める方や、将来的にハードダーツの試合にも挑戦してみたいという方には、ハードボードがおすすめです。
スコアは自分で記録する必要がありますが、そのぶんプロ仕様のリアルな打感を味わえ、耐久性にも優れているため長く使い続けられます。
このように、プレイスタイルや使う人のレベル、設置環境によって最適なタイプは異なります。
自分の使い方に合ったダーツボード、マイダーツを選ぶことで、より快適で楽しいダーツライフを実現できます。

自宅用におすすめのソフトボード3選【静音、スマホ連動モデルも】
家庭用ダーツボードとして特に人気なのが、ソフトダーツボードです。
安全性が高く、電子機能やスマホ連携にも優れており、初心者から経験者まで幅広い層に支持されています。
ここでは、自宅用に最適なソフトダーツボードを厳選して3つご紹介します。
いずれも静音性や機能面に優れ、日常の中で気軽にダーツを楽しめるモデルです。
① DARTSLIVE Home(ダーツライブ ホーム)
家庭でもDARTSLIVEのオンライン環境をそのまま体験できる、高機能な最新モデルです。
【特徴】
- スマホやタブレットと連動して楽しめるホームボード
- DARTSLIVE3でおなじみのグラフィック&サウンドを再現
- オンライン対戦「LIVE MATCH」で世界中のプレイヤーと対戦を楽しめる
② DARTSLIVE-ZERO BOARD(ダーツライブ ゼロボード)
とにかく静音性に優れた、シンプルかつ高性能なボード。投げ心地の良さとコスパの高さが魅力です。
【特徴】
- 静音性能は業界トップクラス。時間帯を選べば集合住宅でも安心
- ボード周りを保護するサラウンドが無料で付属
- 電子式ではなくシンプルな作りのボード。とにかく投げる練習に集中したい人向け
③ GRAN BOARD 3s(グランボード3s)
スマホやタブレットと連携して、世界中のプレイヤーと対戦できる人気モデル。デザイン性にも優れています。
【特徴】
- スマホやタブレットと連動して、多彩なゲームモード&オンライン対戦が可能
- ヒットやアワードなどのアクションがLEDと連動。ゲームを鮮やかに演出
- DARTSLIVE Homeよりも静音性が高い
これら3つのモデルはいずれも、自宅で快適にダーツを楽しめる優秀なアイテムです。
「静音性」「スマホ連携」「オンライン対戦」といった機能の中から、自分の使い方に合った1台を選んでみてください。
本格派におすすめのハードボード3選【プロ仕様・高耐久モデル】
ダーツの本場・ヨーロッパを中心に主流となっているのが、ハードダーツボードです。
ブリッスル素材(麻)を使用し、鋭い金属製のポイントのダーツを使用するため、投げ応えが抜群。
プロトーナメントで使用されるモデルも多く、よりリアルで本格的な練習をしたい方に最適な選択肢です。
ここでは、自宅でも設置できる高品質なハードボードを3点ご紹介します。
① DYNASTY EMBLEM KING Type-NW【451】
日本ブランド「DYNASTY」が手がけた高品質ボード。耐久性・静音性・視認性のバランスが取れたモデルです。
【特徴】
- 最高級Aグレードの麻を使用
- 高いクオリティと耐久性
- ホワイトカラーのブレードで視認性も良好
② Winmau Blade6 Dual Core
世界大会公式採用ブランド「Winmau(ウィンモウ)」の上位モデル。トッププレイヤーからの信頼も厚い一台です。
特徴:
- 圧縮率の異なる2層の盤面構成により、高い耐久性と最適な刺さりを実現
- 極細のワイヤーにより、バウンスアウトを最小限に抑制
- 世界ダーツ連盟の公式仕様に基づいて作られた本格ボード
③ TARGET TOR Dartboard
人気ブランドTARGETのハードボード。「剛性」「美しさ」「耐久性」を高次元で融合させた逸品。
特徴:
- マダガスカル産のサイザル麻でつくられた高品質なハードボード
- 長時間のプレイも優れた自己修復性により美しい状態を保持
- 耐久性の高いステンレス製のスパイダーでバウンスアウトを軽減
ハードダーツボードは、スコアを手書きで管理する必要がある反面、投げ心地はまさにリアルそのもの。
自宅に設置する場合は、音や壁の保護を工夫することで、快適な本格環境を整えることができます。
プロ志向の方や、ハードダーツを極めたい方は、ぜひこれらのモデルを検討してみてください。
ダーツボード設置時の注意点と快適空間の工夫

自宅にダーツボードを設置する際は、正しいルールに基づいた設置方法と、周囲への配慮が欠かせません。
ここでは、快適で安全にダーツを楽しむためのポイントを3つの観点から解説します。
設置距離・高さの基本ルール
まず押さえておきたいのが、ダーツボードの設置高さとスローライン(立ち位置)との距離です。
正確な距離で投げることで、感覚が養われ、実戦や対戦でもブレないフォームが身につきます。
- ダーツボードの中心(ブル)までの高さ:約173cm
- スローラインからボードまでの距離:ソフトダーツ=約244cm/ハードダーツ=約237cm
ソフトダーツとハードダーツで距離が異なるため、お使いのボードのタイプに応じて正確に測ることが大切です。
距離をマットで固定する、床にマーキングするなどの工夫でミスを防ぎましょう。
壁・床へのダメージを防ぐ方法と周囲への配慮
自宅でダーツをするなら、壁や床の保護も重要なポイントです。
ミスショットやバウンドによって、壁に穴が開いたり床が傷ついたりするリスクがあります。
- バックパネルやコルクボードなどを使って壁を保護
- ラグやダーツマットを敷いて、床への衝撃やダーツの落下に備える
- 周囲に壊れやすい家具・家電がないか確認しておくと安心
また、プレイ中に近くに人がいないかなど基本的な安全確認は必ず行うなど周囲に十分配慮した保護対策を取ることをおすすめします。
※ハードダーツは刺さる力が強いため特に注意が必要です。
スタンドやマットとの併用も検討しよう
壁に穴を開けずに設置したい方や、設置場所を柔軟に変えたい方にはスタンドの使用がおすすめです。
- 設置や撤去も簡単なので、引っ越しや模様替えにも対応しやすい
- マットを使えば床の傷の防止だけでなく投げる距離も固定でき、フォームの安定にもつながる
スタンド+マットの組み合わせは、安全性・利便性・快適性を兼ね備えた理想的な設置スタイルといえます。
設置に不安のある方は、スタンドやマットの導入を検討してみてください。
ダーツマシンを購入しなくても、個人で理想のダーツ空間はつくれる!

かつては業務用のイメージが強かったダーツマシンですが、近年は家庭向けのモデルも進化し、個人でも本格的なプレイが楽しめる時代になりました。
静音性に優れたソフトボードや、プロ仕様のハードボード、スマホ連動機能を搭載したスマートな機種まで、選択肢は豊富です。
とはいえ、種類が多いからこそ、自分のレベルや目的に合ったモデルを選ぶことが大切です。
ゲーム感覚で楽しみたいならソフトダーツ、投げ心地を重視するならハードダーツなど、用途に応じて最適なボードを選びましょう。
さらに、スタンドやマットなどの設置アイテムを併用することで、より安全で快適な“自宅ダーツ空間”をつくることが可能です。
壁や床を傷つける心配も減り、正しいフォームや距離感の練習にもつながります。
ぜひこの記事を参考に、あなたにぴったりの家庭用ダーツボードを見つけて、自宅での充実したダーツライフを始めてみてください。